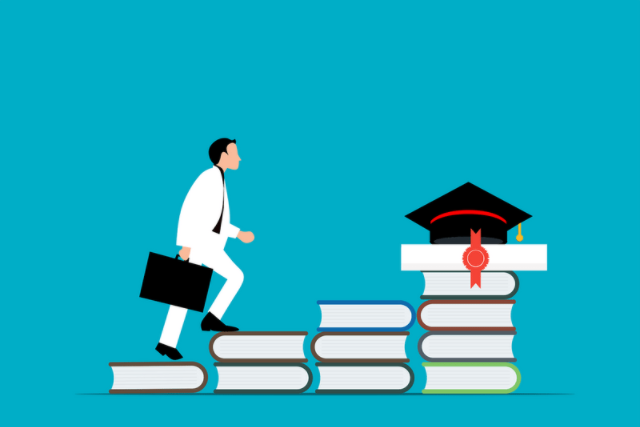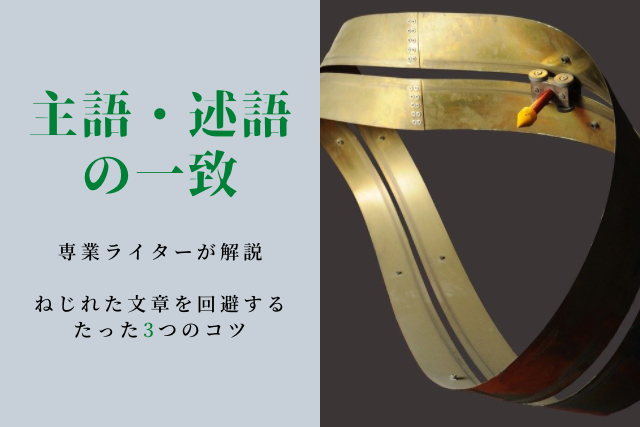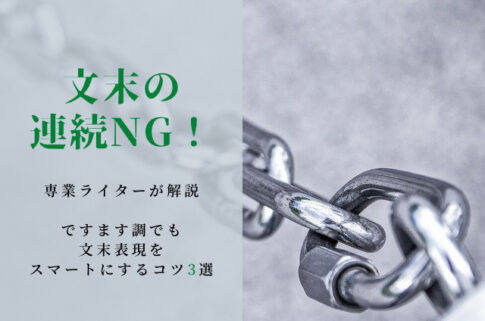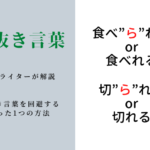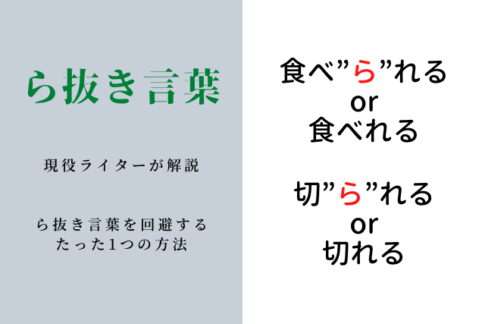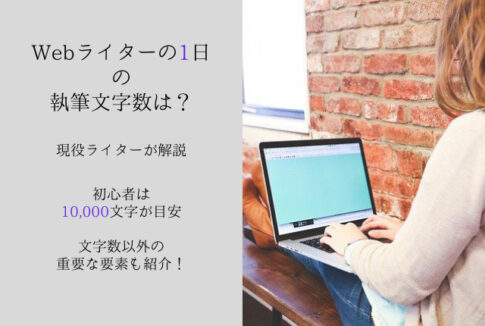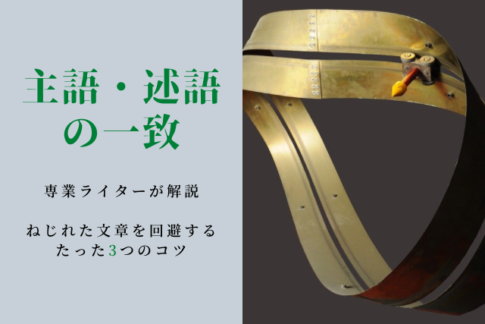- 「クライアントから文がねじれていると言われた」
- 「主語と述語って実際何?」
- 「文章がわかりづらいと指摘されることがある」
Webライターに限らず、文章を書く際に意識するべき項目は「主語と述語の一致」です。
当記事では、主語と述語についてWebライター視点で解説をしていきます。
当記事の内容は下記の通りです。
- 主語と述語の一致は文章の基本!できていないと”ねじれた文章”になる
- ねじれた文を回避・修正するたった3つのコツ
- ねじれた文の見極め方3選
Webライターとして執筆にあたる際、主語や述語などの文法知識がなくて不安という場合はぜひ最後までご覧ください。
主語と述語の不一致(ねじれ)についての問題が解決することでしょう。
Contents
主語と述語の一致は文章の基本!できていないと”ねじれた文章”になる

正しい文章の前提条件として、主語と述語の一致が必要です。
ちなみに主語と述語が不一致なことを「ねじれ」と呼びます。
私は熱いコーヒーを美味しいと思いました
私は熱いコーヒーを飲んで美味しいです
上記の2文を比較すると、前者は普通、後者は違和感があると思いませんか?
違和感の正体こそ”ねじれ”です。
とはいえ、主語と述語がそもそもどう定義されるのか、ねじれがどういうものなのかをしっかり知っておくことが重要。
そこで当記事では主語・述語の定義からお話ししていきます。
※もし、ねじれを解消する方法を先に知りたいという場合は、こちらからジャンプしてください。
主語とは?:動作・作用などの主体を表す語
主語とは……
文において、述語の示す動作・作用・属性などの主体を表す部分
と定義されています。
ようは文の中で動作をする人や物のこと。
主語の例を挙げると
- 私は
- 犬が
などが該当します。
日本語の特徴として、主語が省略されるケースが多い点には注意。
読解できてしまうのも相まって、自分で文章を書くときに主語を省略してしまう方が結構いるものなのです。
この間、(私は)遊園地に行きました。
(遊園地が)とても楽しくて、また遊園地に行きたいと(私は)思いました。
上記の()の中が省略された主語です。
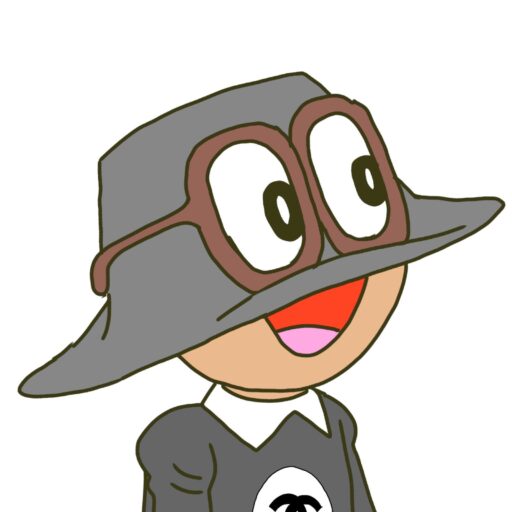
しかし主語の省略をしてしまうと、読者が文章を読む際に主語を考える手間が生じてしまいます。
そのため、なるべく主語の省略は行わないようにしましょう。
述語とは?:動作・作用などを表す語
一方で述語とは……
主語について、その動作・作用・性質・状態などを叙述するもの
と定義されます。
動作や状態を表し、動詞・形容詞などが述語にあたるものです。
述語の例を挙げると
- 走る(動詞)
- 泳ぐ(動詞)
- 美しい(形容詞)
- 楽しい(形容詞)
- Webライターだ(名詞+助動詞)
といった感じ。
述語の方は省略されると文章が通らなくなるので、あまり執筆時に気にする必要はありません。
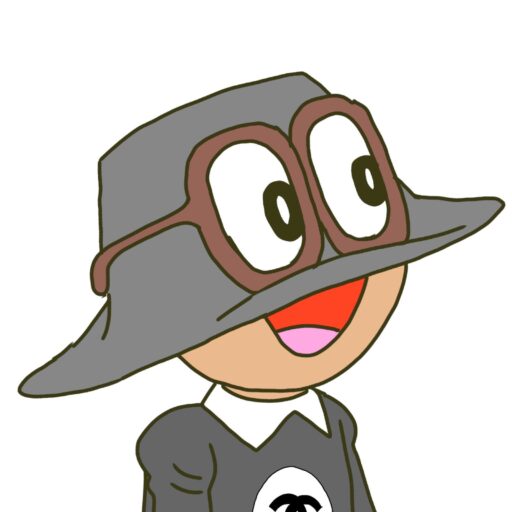
文のねじれとは?:主語と述語が対応(一致)していない状態
主語と述語はワンセットです。
主語と述語が不一致な状況をねじれと呼びます。
ねじれた文の例をもう一度挙げると下記の通り。
私は熱いコーヒーを飲んで美味しいです
主語「私は」に対して、述語「美味しいです」は対応していないのがわかりますか?
一方、主語を「コーヒは」に変えて文章を微調整すると……
私が飲んだ熱いコーヒーは美味しいです
となり、違和感がなくなりました。
上記のように文の主語と述語を”必ず”一致させる必要がWebライターにはあります。
なぜ”必ず”なのかについては次項で説明しましょう。
文がねじれるとどうなる?
結論を言ってしまうと、ねじれた文はWebライターにとって論外です。
そもそも内容を判断する土俵にすら立てません。
なぜそういえるのか、ねじれの文が与えるネガティブな事象についてまとめました。
下記3項目が挙げられます。
- 文章の意味が通じづらくなる
- 文章を稚拙に感じる
- 【結果的に】Webライターとして低スキルだと思われる
文章の意味が通じづらくなる
まずは文章の意味が通じなくなるという点。
文がねじれると「誰が何をしたのか」という基本が読み取れなくなります。
そのため、ねじれた文は必要以上に読者に読解を強いることになってしまうのです。
Web記事の読者は読解をしたいわけではありません。
できるだけ簡潔に情報を求めている中、ねじれた文があればすぐさまページを離脱することでしょう。
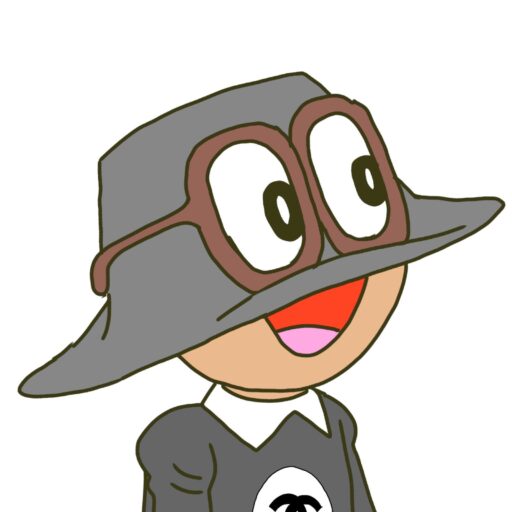
文章を稚拙に感じる
意味が通じにくいという点とあわせて、文章が稚拙になるというデメリットもあります。
小学生くらいの国語をまだ学んでいる段階の子どもたちは、主語・述語の認識が甘いので、ねじれた文を書きがちです。
そういったイメージもあり、ねじれた文=稚拙な文といった認識になっているわけ。
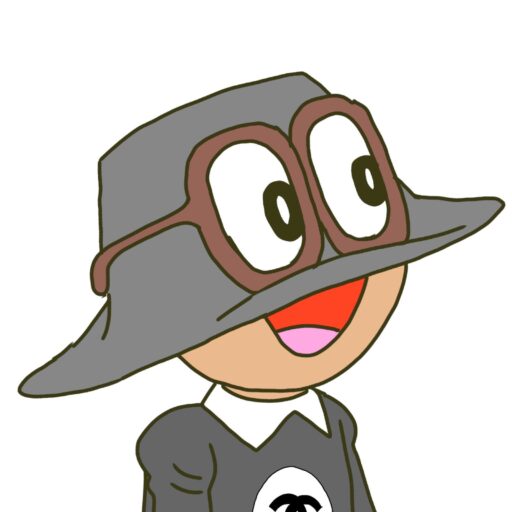
【結果的に】Webライターとして低スキルだと思われる
上記の
- 意味が通らない
- 文章が稚拙になる
といった事象から、結果的にねじれた文を書くWebライターは低スキルだと判断されてしまいます。
どれだけ調査をして、品質の高い情報を持っていたとしても、ねじれた文ではそもそも内容を評価してもらえません。
それだけ文のねじれはWebライターにとっては大敵。
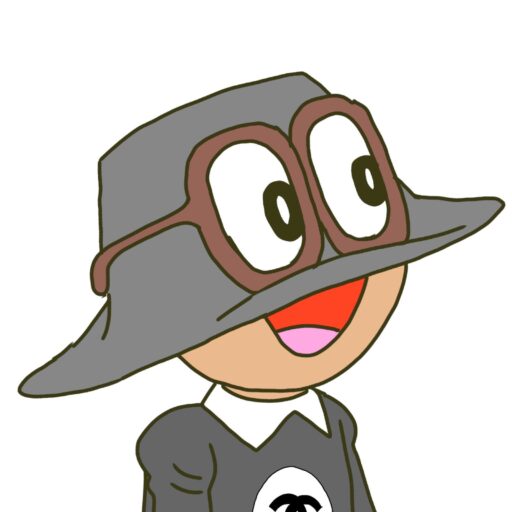
ねじれた文を回避・修正するたった3つのコツ
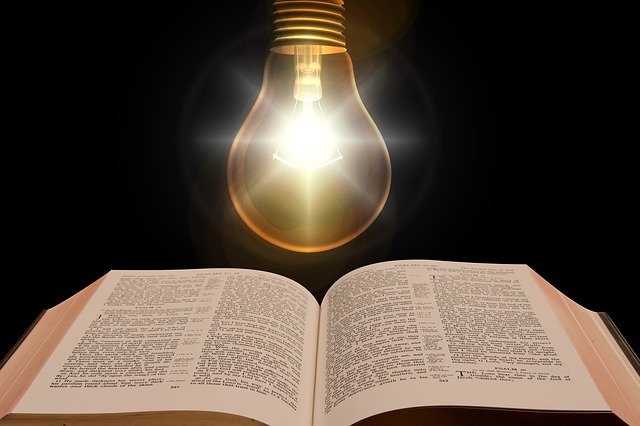
さて、ねじれた文について理解が深まったところで「どうすればねじれを回避できるの?」という疑問にお答えしていきましょう。
結論として下記3つのコツを意識してみてください。
- コツ①:文を短くする
- コツ②:主語と述語を決めてから文を構築していく
- コツ③:一文一義を意識する
1つずつ説明していきますね。
コツ①:文を短くする
まずは文を短くする意識を持ちましょう。
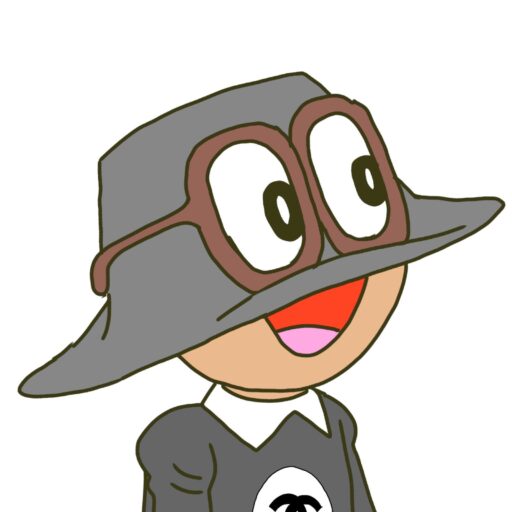
そもそも文がねじれるのは、文が長くなってきたときです。
主語と述語の物理的な距離が離れれば離れるほどに、ねじれは起きやすくなります。
そもそも文が短いと、ねじれが起きづらいという話。
ちなみに、一文の長さ(文字数)は60〜70文字程度がベストと言われています。
フォントサイズや画面の表示領域にもよりますが、基本的には「一文がPC表示で3行またがったらアウト」と考えるといいでしょう。
イメージは下記のような感じです。
私はヒキライターといい、大学院を中退してから未経験でWebライターの業界に入りましたが、4年経った今では専業ライターとして生計を立てることができていまして、ヒキライターというブログで初心者ライターに貢献できればと思っています。
上記は文が長すぎて、どれが主語か述語かも非常にわかりにくいものです。
例のような文では、読者に多大なストレスをかけてしまい、離脱されてしまうでしょう。
私なら下記のように書き換えます。
私はヒキライターといいます。
大学院を中退してから未経験でWebライターの業界に入りました。
しかし、4年経った今では専業ライターとして生計を立てることができています。
ヒキライターというブログで初心者ライターに貢献できればと思っています。
書き換え方のポイントとしては、文を細かく区切り、必要があれば接続詞を追加するというものです。
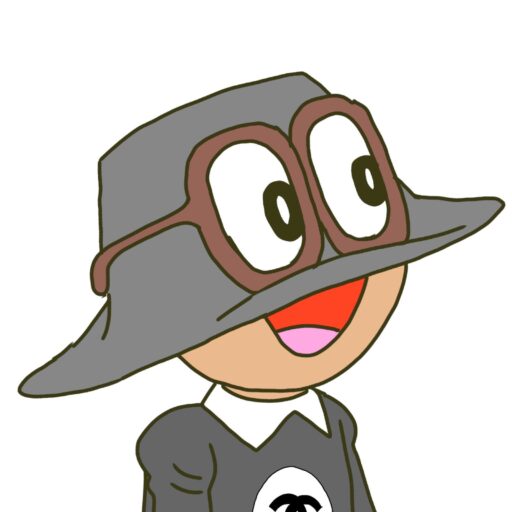
コツ②:主語と述語を決めてから文を構築していく
次のコツは「主語と述語を決めてから文を書く」というもの。
行き当たりばったりで文を構築すると、どうしてもねじれていきます。
そこで、文の最小構成単位である主語と述語から文を組み立てましょう。
伝えたい要素が下記だとします。
- 私
- 友達
- 日曜日
- 遊園地
- 行った
- 夕方まで
- 遊んだ
- 楽しかった
- また行きたい
- 約束をした
まずは上記の要素から主語と述語を引っ張り出します。
私は行った。
私は遊んだ。
遊園地が楽しかった。
私は約束をした。
主語と述語が確定したら、要素を当てはめていきます。
私は友達と遊園地に行った。
私と友達は夕方まで遊園地で遊んだ。
遊園地が楽しかった。
私と友達はまた行きたいねと約束をした
主語がくどいように感じるかもしれませんが、一応ちゃんと書くと上記のようになります。
今回の手順で文の構築をすれば、少なくとも文がねじれることはありません。
コツ③:一文一義を意識する
文を短くすること、主語と述語から組み立てることを意識すれば自然となることではありますが、一文一義も意識しましょう。
一文一義とは、
「一文一義」というのは“一つの文章に一つの情報だけを書く”こと
と定義されています。
一文一義から反した文は下記のようなものです。
私はヒキライターといい、大学院を中退してから未経験でWebライターの業界に入りましたが、4年経った今では専業ライターとして生計を立てることができていまして、ヒキライターというブログで初心者ライターに貢献できればと思っています。
先ほど長文の例で出したままの文です。
接続助詞(「が」など)を多用して文を接続しているのが良くない点。
一文一義にするなら、先ほど行ったように下記のようにすればOKです。
私はヒキライターといいます。
大学院を中退してから未経験でWebライターの業界に入りました。
しかし、4年経った今では専業ライターとして生計を立てることができています。
ヒキライターというブログで初心者ライターに貢献できればと思っています。
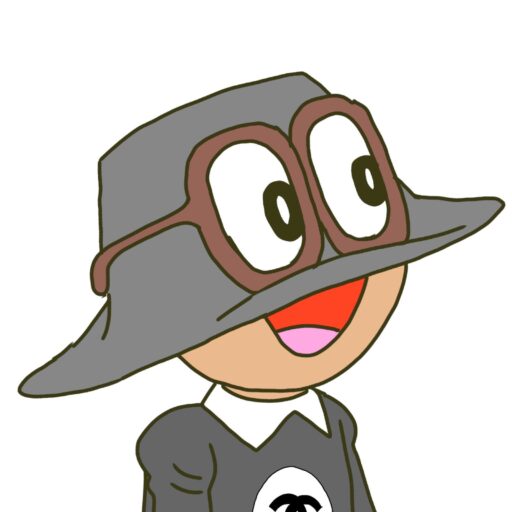
ねじれた文の見極め方3選

最後にねじれた文の見極め方をお伝えします。
というのも、そもそもねじれているかどうかの判断ができなければ、改善のしようがありませんよね。
ご紹介する見極め方は下記3つです。
- 主語と述語だけにしてみる
- しっかり音読して読み返す
- 他人に読んでもらう
それぞれしっかり押さえておけば、ほぼねじれを見極めることができるでしょう。
主語と述語だけにしてみる
まずは主語と述語の抽出です。
最初は述語がベストでしょう。
先ほど説明した通り、主語は省略できてしまうものなので、書くのを忘れている場合があるからです。
述語を探す→主語を探す→一致しているか判断する
といった流れでOK。
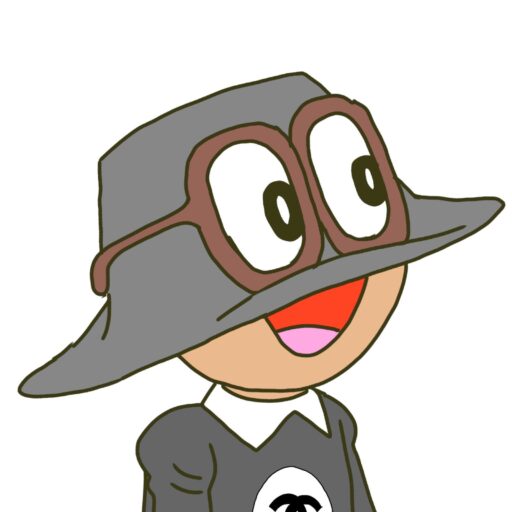
しっかり音読して読み返す
主語と述語の不一致、ねじれは音のリズムでも違和感を覚えるものです。
そのため書いた記事は音読で読み返す癖をつけましょう。
音に出して読むことでねじれだけでなく、文末の連続や誤字脱字についても敏感になれますからね。
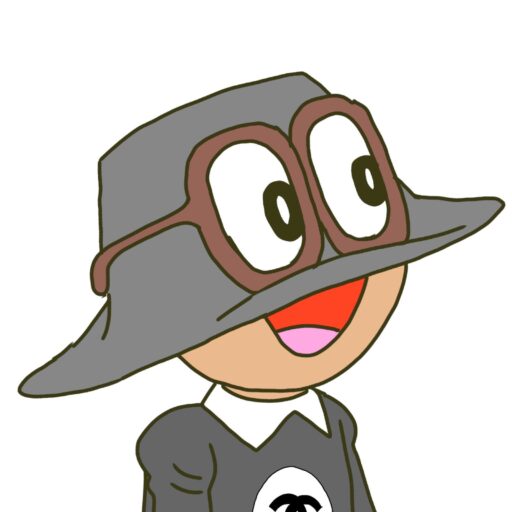
他人に読んでもらう
最終手段は他人に読んでもらう方法があります。
こちらは、自分で気づけないようなミスでも一撃で指摘してもらえるのでおすすめ。
ちなみに、Web記事の基本「誰に読んでもらっても理解できるような文章かどうか」を確かめるという意味でも重要な方法です。
たとえば、内容が頭に入ってこないといった問題が生じた場合は
- 前提情報が足りない
- 言葉が固すぎる
- 文章のクオリティが低い
などの原因が考えられます。
そのまま納品したら、クライアントから信頼を失くすようなケースも、他人に読んでもらうことで回避できます。
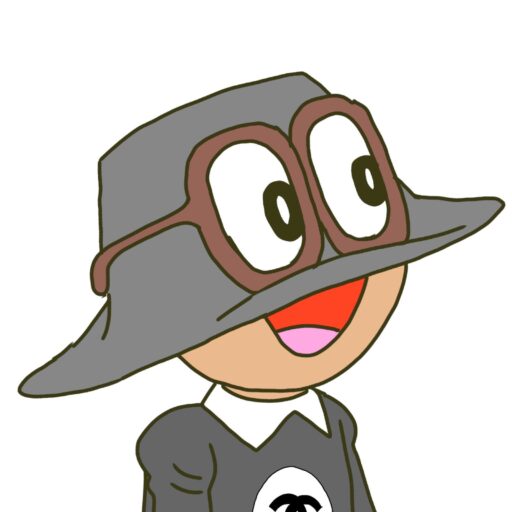
まとめ:主語と述語の一致は文の基本!ねじれた文を書かないようにしよう

主語と述語の一致はWebライターの基本です。
ねじれた文章を納品したら、信頼を一気に失うケースもあります。
テストライティングでは、そもそも内容評価以前の問題です。
そんな恐怖のねじれですが、回避する方法は下記の通り。
- コツ①:文を短くする
- コツ②:主語と述語を決めてから文を構築していく
- コツ③:一文一義を意識する
また、ねじれを見極める方法は次です。
- 主語と述語だけにしてみる
- しっかり音読して読み返す
- 他人に読んでもらう
上記を押さえて、ねじれのない文章を執筆するように心がけましょう!
当記事のようなWebライターについてのノウハウについてまとめたページがございます。
あわせてご覧ください!
当記事はここまで。
最後までご覧くださってありがとうございました。
それではまた!